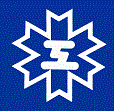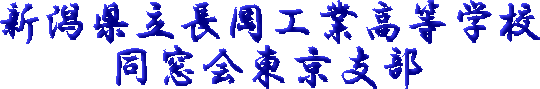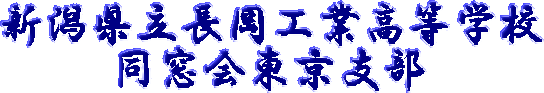先輩から
第81弾です。なお今後も定期的に投稿を掲載して行きます。どうぞご期待ください。
第81弾「タイヤ機械」
松永 巌

昭和三九年(一九六四)三菱三重工合併後暫く経った或る日、直属の上司である長崎造船所の末永副所長から呼び出しを受けた。私は当時機械管理課長と言う職にあり、合併時の機種統合や合理化の仕事に携わって居た。
副所長より「合併も出来たし、合理化も旨く行って居る。これからは管理過剰となるので、君は設計に戻って呉れ。然し君も知っての通り、君の所属して居た水車は高砂製作所に統合される。君は課長であり、高砂で水車の設計と言う理由には行かない。幸町にニ万坪の土地がある。こゝに船、原動機(タービン、ボイラー、ディーゼル・エンジン等)以外の第三の柱を作る様にやって呉れ!!」と大きなプロジェクトを依頼された。
幸町工場は浦上駅に程近く、浦上川とJR長崎線が西側を走る市街地にあって、当時はボイラー・チューブの加工の他、当時の防衛庁の特定工場として、魚雷、ロケット・ランチャー等を製造して居た。工場を一杯にするには量産が出来るものとし、自動車関連、食品関連、環境関連があるが、既存メーカーが多数あり仲々難しく、結局自動車関連のタイヤを作る機械をやろうと言う事になった。
タイヤ機械とは生ゴムで作られたタイヤに熱と圧力を加えて弾力性を持たす様にする加硫機と言う機械が主力である。
昭和四〇年(一九六五)一ニ月一五日付産業機械設計課長を拝命した私は早速課員を集めタイヤ機械をやる話をした。課長代理の堀昭君は旦って〇社のタイヤ機械の修理の圣験があり多少の知識があった。彼の話に依ると日本では米国のマックニールと技術提携をして居るK社一社だけ、しかも「機械を使用してタイヤを作る事」と言う基本的な事が特許になって居り、他社では出来ないと言う。
それは大変な事だと私自ら、その特許公報を取り寄せて調べた。そしてその特許は私が設計課長就任のニ日前に切れて居る事が解った。これは大発見で一つの山を越え「これは行ける!!」と確信し、更に米国へ行って詳細に調査する必要があると思い、副所長に報告、渡米の許可を貰った。
昭和四一年(一九六六)五月一三日NW〇〇六便にて出発、オハイオ州アクロンに向かった。こゝには米国有数のタイヤ・メーカーの本社、工場が集って居り、タイヤ機械メーカーも此処にあった。例のマックニールと市場を二分するナショナル・ラバー・マシナリー(NRM)社もあり、私の目的はこの会社を訪ね技術提携の可能性を探る事であった。
NRMは従業員一〇〇名程の中小企業ではあるがタイヤ機械では著名であった。本社は黒壁のこじんまりした二階建の質素なもの。
社長は長身の堂々たる紳士。ゴルフもハンディ2の名手と聞いたが、極めて気さくな方で私の名前の「巌」から”ROCKY”と英語名を付けて呉れ、その後長い付合となったのである。彼は提携に就いて「基本的には大賛成であるが、例の基本特許の外に、どうしても避けられない特許が未だニ件あり、NRMも使用許可を得て居り、三菱も再許可を得なければならない。然し自分が話を付けてやるから心配するな」と約束して呉れた。私は交渉は成立したものとして本社に報国し帰国の途に就いた。
帰国するとK社が三菱がタイヤ機械をやる事を知り、マックニールに技術提携の再許可をしない様に動いて居る事を知った。私もニつの特許に就いて技術的に検討したが回避は不可能であった。一方NRMからは仮契約を締結し図面や資料が送付されて来て、Y社から四基の受注が決まり製造も進んで行った。
機械が完成し、据付の段階でK社が裁判所を通じて工事差し止めを掛けて来て一時中断する事態となった。仕方なくK社と直接交渉をする事になって少し時間は掛ったが、目出度く解決し、昭和四ニ年(一九六七)一一月NRMターク社長が来日、築地の新喜楽で正式調印の運びとなった。
翌年早々B社の仲嶋常務が直接私の所へお越しになり、「九州の鳥栖にラジアル・タイヤの新工場を建てるのでニ〇〇基の加硫機が必要ですが出来ますか?」との夢の様なお話。勿論私は「是非ともやらせて頂きます」とお答えし営業を通して正式に契約、幸町工場はフル稼働、受注も増加、順調に拡大、ブラジルの三菱でも製造する迄に発展した。
私はタイヤは外見は単純に見えるが、色々な部材を組み合わせて造るため、色々な工程で色々な機械が必要な事を知った。しかもラジアル・タイヤの普及により、新しい機械が必要である事も知った。ラジアルは米国より欧州が先行して居て、欧州のメーカーとの提携が必要と考えた。その結果、イタリーのピレリー社とラジアルの成形機、フランスのガズイ社とゴムシートの裁断機、ドイツのワーナー社と生ゴムの混練機等の技術提携を進めた。そして数々の機械の集積された、タイヤ工場全体、つまりタイヤ・プラントの受注をすべきと考えた。然し残念乍ら私は本社に転勤する事になり、止むなく技術面は私の後輩の長谷川昭君に、営業面は澤本嘉文君に懇々と説明して託した。又製造ノーハウに就いては某タイヤ会社にお願いし数名の専門家に出向して頂く事にして、体制を整えて転勤した。
本社に転勤後、米国駐在となったが、昭和五一年(一九七六)の夏、澤本君から夜国際電話があり、「松永さんと言って居たタイヤ・プラントをルーマニアから初めて受注した」と涙声での報告を受け、私も声を詰まらせお礼を言い、今後も頑張る様激励をした。
長崎造船所の第三の柱と迄は行かずとも大きく発展し三菱重工の主要事業となり、提携先のNRM社の買収までして米国内にも事業を展開する迄になった。
然し永い年月の間に中国のメーカーが立ち上がり、現在では殆どの機種は中国で作られて居るとの事である。一時は命を掛けて頑張って来た事を考えると、時の流れとは言へ、感慨無料である。
2024.12.10