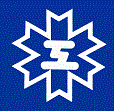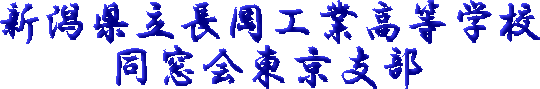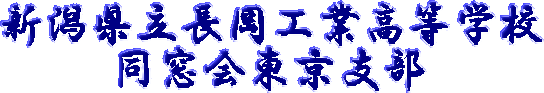先輩から
第51弾です。なお今後も定期的に投稿を掲載して行きます。どうぞご期待ください。
第51弾「ポータブル蓄音機」
松永 巌

令和二年十二月号に「御萩」と題して書いた。その時に訪ねた姉の家に「ポータブル蓄音機」なるものがあった。
古い話になるが幼少の頃の生家に、大正時代に購入した蓄音機があった。重さも一〇瓩程もあり、とても持ち歩ける品物ではなかった。固い樫の厚い板で作られた箱で、回転盤の付いた上蓋は前を上げて開ける様になって居て、裏側には回転盤を駆動する機械があり、大きな発条(ゼンマイ)を動力とし、この発条を撒くハンドルがあった。
姉のポータブルは、徹底的に小型化、軽量化が図られて居り、外箱の厚みも薄く、高さも重量も半分位になって居た。ハンドルも水平では手が床面に付くので、斜めに差込み楽々廻せる様な旨い設計になって居た。
当時ラジオはあったが、蓄音機は洋楽だけではなく、童謡、浪曲等もあり、欠かせぬ娯楽製品であった。
姉にお願いしてこれを借り殺風景な寮に持ち込んで、皆を楽しませてやろうと考えた。
姉は快く承諾し、子供たちの了解も得た。
蓋をすればトランクの様になり、把手も付いて居て、本当にポータブルであった。数枚のレコードも借りて、寮に持ち帰った。
同じ寮に東大法学部の人達も居たので、幹事役の船橋尚道と言う人に話をし、一緒にレコードコンサートをやろうと言う事になった。同級生に日本光学(現ニコン)の白浜浩社長の息子が居り「親父がドイツで集めたレコードが沢山ある」と言うので、東京の自宅から持って来て貰った。憲兵が居るので余り派手には出来ないが「帰れソレントへ」とか「オーソレ・ミオ」「アベ・マリア」等の小曲が主体であったが、中にはベートベン、シューベルト、ショパン等の名曲もあった。
何回か夜に実施したが、本当に何もない寮で大きな役を果たしたと思う。
やがて終戦となって、借りたレコードは全部返却したが、ポータブルは持ち帰らねばならない。布団等は後送されるが、身の回りのものはリュックとトランクに詰め込んだ。
皆はトランク一つなのに私は二つ。寮のある小泉から高崎線の熊谷まで東武妻沼線と言う短い私鉄があったのだが八月一五日の〇時過ぎ熊谷市は大空襲で壊滅、不通となって居た。熊谷まで約三〇粁、歩くしか無い。
しかし昼は炎天下、学校教練で経験した夜間行軍を選んだ。背にはリュック。手にはトランクとポータブル、満杯の水筒を肩に、八月一七日夜八時寮母に別れを告げて単身出発、今の国道四〇七を只菅南へ、途中利根川の橋を渡り、熊谷市街に差し掛かると、一五日空襲の後の焦げ臭い匂いがして居た。駅に着いたら夜が明けた。約三〇粁、一〇時間歩き続けた。今ではとても考えられない時間と距離である。
暫く待っていると満員鈴生りの列車が入って来た。乗れそうもない!その時車内から兵隊が声を掛けて来た。「水筒に水が入っているか?」と。「入っている」と答えたら「一口飲ませて呉れ、そうしたら足二本分だけ場所を空けてやる。荷物の場所は無いぞ!」と言う。「解った!」と言って胴に巻いて居た三尺帯で二つの手荷物を振り分けにして窓の外にブラ下げ、躰だけを車内に引っ張り込んで貰った。荷物はぶつかって毀れたらそれ迄と思って居たが郷里の見附駅(新潟県)迄無事着いた。家に帰って話をしたら皆に笑われたが、学校が始まるまで毎日の様にレコードを掛け楽しんだ。
やがて東大に入学し、浦和の姉の所に下宿する事になり、借りたポータブルも持参し、礼を言って返した。
法学部の船橋さんとはその後も文通を続け、大学進学への指針も頂いた。一年の時、東京帝国大学が東京大学に名称が変わった頃に色づいた銀杏並木のキャンバスで偶然お会いし、久闊を叙する事となった。船橋さんは既に就職も政府系の「社会問題研究所」に決まっていると仰って居た。日本労働法の識者として後法政大学教授に成られたが平成一〇年病に斃れられた事を新聞の訃報で知った。
二〇二一・一二・四