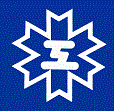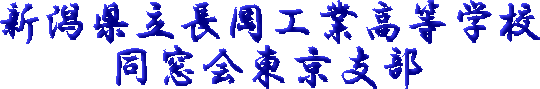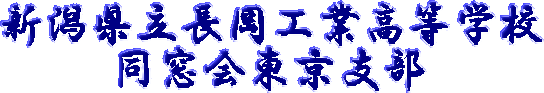先輩から
第3弾です。なお今後も定期的に投稿を掲載して行きます。どうぞご期待ください。
第3弾「欧州へ(南回り)」
松永 朔風(巌)

入社して八年目の昭和三十五年一月の或る日、部長に呼ばれて部長室に入った。何の話だろうと部長席に近付き、直立姿勢で待って居ると、部長は椅子に座ったまま私の方を向いて、突然「松永君、君スイスに行って来いよ」と言われた。行き先や目的は仕事の性質上、薄々解って居たが、念の為に「目的は何でしょうか?」と尋ねた。部長は「特別な目的は無い。君が現地に行って自由に見聞した上で、自分でテーマを決めなさい。期間は四月一日から半年間だ」と言うご返事。
実は大学院を修了し、担当教授に就職先をお願いした時に「この会社はスイスと技術提携をしたから、君は入社したらスイスに生けるかも知れないよ」と示唆されたことを思い出し「ああ、教授の仰しゃる通りになったなあ!」と感慨無量なるものを感じた。
出発まで三か月、部長は現地でテーマを見つけろと言われたが、自分としては日頃考えていたことがあったので、それ等の予備知識を身に付けることを考えた。少し専門的になるが、昭和二十八年入社以来、電力会社や公益事業の発電用水車の設計に従事して居た。
水力発電とは高所から流れる水で水車を回転し、発電機を駆動して発電することであるから、そのような地点を探し、高さに依って水車の形式を選び、最大水量に依ってその大きさを決め、あとは詳細設計するのである。
しかし当時狭い日本では高い地点の開発は殆ど済んで居り、利用可能な地点は極端に乏しく、残って居るのは低落差、大水量の河川のみであった。所が、その様な地点の水車を設計すると、水車が巨大となり、しかも回転数も低くなり駆動する発電機が大きくなり採算が取れなくなる。私はこの様な場合でも回転数を上げて発電機を小さくする方法がないかと考えて居たので、この低落差開発を研究テーマとする事とした。
行く先はスイスのチューリッヒにあるエッシャー・ウィス(現スルツァー社)と言う世界屈指の水車メーカーである。出発の日までに、既に訪問経験のある諸先輩を訪ね、仕事以外の事も含め、色々親切に説明を受け、使い残しのスイス貨幣も頂いた。会社からは当時としては相当な支度金なるものを頂き、背広や靴などを新調し、学生時代の持ち物から脱却した。
昭和三十五年四月十五日、会社の上司や同僚に見送られて長崎駅を出発(当時長崎では海外出張者や転勤者を駅で見送る習慣があった)東京に一泊し、翌十六日関係者が羽田まで見送りに来て呉れた。
羽田は漸く新館(現在の旧館)が出来た頃であった。日本航空には未だ国際線は無く、欧州に行くにはエア・フランス(仏)、BOAC(英)などジェット機による北欧経由と、スイス・エアなどプロペラ機による南廻りがあった。スイス訪問の経験のある課長は「将来南廻りは無くなるだろうから、話の種に南廻りで行ったらどうか」と親切に奨めて呉れたので、それに従い南廻りのスイス・エアに決めた。課長はまた自分の経験からか「松永君はドイツ語が出来るかも知れないが、スイスでは絶対に使うなよ、彼らは自国語だからペラペラ喋ると聞き取れなくなるぞ!」とも教えて呉れた。
さて四月十六日、愈々飛行機に乗る時が来た。夜十時四十五分羽田発SR503便チューリッヒ行き(機種DC6、四発のプロペラ機)であった。DC6は台湾へ出張の時乗った経験はあるが、これでスイスまで行くのかと思った時少々頼りない様な気もした。クルーは勿論全部スイス人、彼らの会話も当然ドイツ語(実際はスウイーチルドイチと言ってスイス訛りのドイツ語)。席に着いたら喉が渇いたので水を所望しようと思った時、課長が絶対ドイツ語を使うなよと言って居たのを思い出したが、飛行機の中位ならと考え、パーサーに「水を一杯下さい」をドイツ語で(アイングラース・パッサー・ビッデー)と言ったら「勿論!ドイツ語上手ですね」(ヤボール! シュプレッヘン・シィエネドイチェ)と通じ嬉しくなって、以後チューリッヒに着くまでドイツ語を使った。
この便は途中、香港、バンコック、カルカッタ、カラチ、カイロ、ジュネーヴに立寄り給油、整備、クルーの交替等があり、羽田からチューリッヒまで四十八時間の予定であったが、予定通り到着した。今考えても本当に長旅であったが色々なことを知ることが出来たので南廻りを奨めて呉れた今は亡き課長に感謝して居る。香港、バンコックは夜中で余り記憶に残るものは無いが数十分程度の整備待ち、カルカッタは昼で飛行場に降りた時蒸し風呂の様に暑かったのを憶えて居る。
連絡を受けて居たらしく商社の駐在員が空港まで会いに来て呉れた。この辺りまで来る日本人が少なかった時代であった。カラチからカイロまでは再び夜間飛行となり、アラビア砂漠の上を延々と飛んだ。一、二時間仮眠をして窓外に向けると、エンジンの排気管が真っ赤に焼けて居るのが見え、下を見れば砂漠が黒ずんだ海の様に見え、砂丘が波の様に見えた。この様な状態が何時間も続いてカイロに夜明けに着いた。空港は一面アラビア文字で異様な感じがした。あと一飛びでヨーロッパ。やっとジュネーヴに着いた時、一緒に乗って居た日本人が全部降りた。結局羽田から最後まで飛び続けたのは私と飛行機だけ。乗客は勿論、クルーは途中何回か交替し、私と最初に会話を交わしたパーサーも途中で居なくなって居た。
現在では考えられない飛行機での四十八時間の独り旅であった。